【島崎英純】2024Jリーグ第19節/浦和レッズvs鹿島アントラーズ・試合レビュー『黄金の左がチームを救う。痛恨のドロー劇の中で見えた微かな光』

©Yuichiro Okinaga
窮屈な攻撃
ホームゲームにもかかわらず、浦和レッズの選手たちの動きは緩慢だった。鹿島アントラーズの4-4-2スライド式ディフェンスブロックを揺さぶれずに各駅停車のビルドアップを繰り返していく。浦和の選手がパスレシーブした眼前には必ず相手選手が立ちはだかっていて、その都度横、もしくは後方へボールを動かして様子をうかがう構えが続いた。浦和は二次的、三次的なアクションが乏しく、自らがボール保持した後の展開予想が出来ていない。それはワンタッチプレーの希薄さに表れており、その判断の遅さが鹿島のディフェンス形成を容易にさせていた。
相手バックライン裏を突くフリーランニングは見られたが、それに呼応して空いたスペースを活用しようとする選手が見当たらない。裏抜けはそこへボールを付けるだけでなく相手バックラインを下げさせる効能もあるわけだから、それに準じてミドルスペースが広がるはずである。ならば、そこへ選手が飛び込んで次なるアクションをも起こすべきだが、浦和の攻撃は一つひとつのプレーが単発で連動性がないから、『裏抜け』が単なる個人アクションに堕し、有効なスペースを活用できない。
負傷者が続出している状況がチーム編成を難しくしている。今回は安居海渡がアンカーに入り、岩尾憲が左インサイドハーフを務めた。この二人のプレーアクションはそれほど悪くはなかった。味方センターバック2枚と相手前線2枚の2対2状況の前方に陣取って前傾姿勢を取った安居の判断は的確だったし、頻繁に上下動して先述した『裏抜け』と後方降りのパスレシーブを繰り返した岩尾の献身性も目立った。ただし、左サイドバックの渡邊凌磨と左ウイングの大久保智明が同レーンに並ぶポジションを取ったのは悪手だった。これは右サイドのオラ・ソルバッケン&石原広教も同様で、彼らがパスアンゴルを付けられないことでサイドエリアからの前進コースが限られてしまった。
(残り 4460文字/全文: 5343文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。
タグマ!アカウントでログイン
- « 次の記事
- 【どなたでも観られます!】『浦和レッズ、鹿島戦ドロー。様々な移籍・獲得報道が飛び交う中、坪井慶介さんと前半戦を総括する LIVE!』/6月24日(月)21時スタート! 続けて会員限定ライブも配信致します!
- 前の記事 »
- 『先発選手の停滞感、交代選手の活躍』2024Jリーグ第19節/浦和レッズvs鹿島アントラーズ・浦和レッズ全選手採点


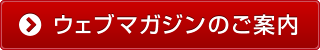
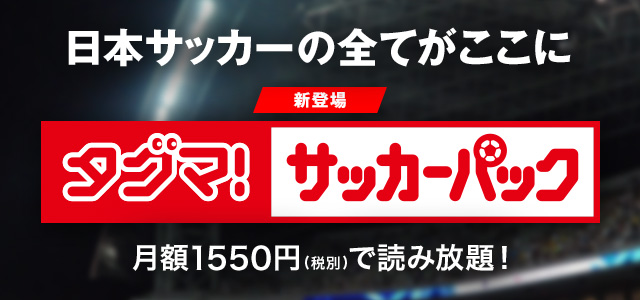









外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ