京都にも中2日の日程にも勝利、「ミスをしないスピード」の大切さ【轡田哲朗レッズレビュー/J第20節 京都戦】
(Report by 轡田哲朗)
マチェイさんが「リスクのある決断」と話した中2日のスタメン継続
浦和レッズは4月16日にリーグ戦の11試合目となる京都サンガF.C.戦に2-1で勝利した。節単位でいくと第20節のゲームだが、今季は浦和がクラブ・ワールドカップ(W杯)に出場する関係で先行開催されるゲームがあるので、この京都戦もその1つ。今後もAFCチャンピオンズリーグ(ACL)関連の大会に出場するチームとの兼ね合いなどでズレることがあるので、節の数と消化試合数が一致しないタイミングは「●試合目」という形にしていく。
このゲームは浦和が13日の日曜日にFC町田ゼルビア戦を消化し、京都は12日の土曜日に湘南ベルマーレ戦が組まれていたので、インターバルが1日違った。9日と16日にはルヴァン杯があって、そこに挟まる先週末のゲームを金曜日から日曜日の3日間分散開催にしたことで、色々なところに「それは公平性の観点からどうなんですか?」という対戦カードが生まれていたので、興味がある方は見ていただくと良いと思う。
色々なことを直前で決められるヨーロッパの主要リーグとは、スタジアムがクラブの所有物でない場合がほとんどであることや、チケット販売や日程確定に関する社会的背景が違い過ぎる面もあり根本的な解決は難しいのだけど、少なくとも同じカテゴリーは同じ日に消化すべき週末だっただろう。付け加えるなら、J2とJ3を土曜日、J1を日曜日に開催しても良かったとは思うけれども。いずれにせよ、浦和は京都だけでなく中2日のスケジュールとも戦う必要のあるゲームだった。

そうした中で、マチェイ・スコルジャ監督は町田戦からのスタメン継続を選択した。何なら、ベンチメンバーも合わせた20人が全く同じで、マチェイさん自身が試合後の会見で「risky decision(リスクのある決断)」だったと話していた。追い回してくるタイプの京都が相手だったとはいえ、町田戦の良かったイメージを壊したくなかった部分があったのだろうし、そのチームの表情を60分から75分にわたって維持しようとした時、互換できるメンバーが意外と少ないことを感じているのかもしれない。
左右の人数バランスの違いと、京都の勢いを利用したプレー
基本的にこのゲームの構図は、京都のハイプレスを浦和がどのように処理できるかという面が強くなった。誤解を恐れずに言えば、京都は相手にストレスを掛けてミスをさせることで自分たちに有利な方向へ試合を組み立てるタイプのチームに見えている。そのストレスの掛け方がハイプレスであり、リーグでトップを争うイエローカードを集めるプレーぶりにもある。なにしろ、浦和戦の前の10試合で彼らは18枚のイエローカードを出され、そのうち10枚は「C2(ラフプレー)」によるもの。ただ、これを嫌がってロングボールに逃げるようなプレーを増やしてしまうと上手くいかなくなる。それは、2月の対戦を思い出せば理解できるだろう。
(残り 3722文字/全文: 4949文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


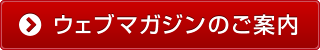
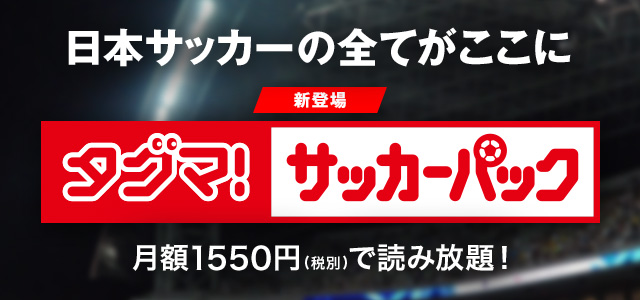







外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ