いずれも解決できなかった盤面と局面、現在と未来を見据えて【轡田哲朗レッズレビュー/ルヴァン杯準決勝第2戦 C大阪戦】
(Report by 轡田哲朗)
基本的にスコアはどうでもいいが、その過程が厳しい
浦和レッズは25日のルヴァン杯準決勝第2戦、セレッソ大阪とのホームゲームに0-4で敗れ、2試合合計1-5で敗戦した。このようなカップ戦は突破か敗退かが重要でスコアは基本的にどうでも良いのだけど、1%の突破可能性を得るために背負ったリスクでこうなってしまったという感がピッチ上になかったことがスコアの不快感に対する原因だろう。例えば、0-2になった後にセンターバック2枚を残して敵陣にものすごい人数をかけて何とかしようとした結果、カウンターで失点を重ねたというのならどこか仕方ないと思える部分もあるだろうけれども、ほとんどの時間帯でそこまで極端なことをやったわけでなくこうなってしまった。
このゲームでは21日に1-1で引き分けた初戦のメンバーからダヴィド・モーベルグが欠場して松崎快がスタメンだった。松尾佑介が前線、関根貴大がサイドバックで起用されたことによって5人目のサイドハーフになってしまっていた彼にチャンスが来たのは良いことだったとは思う。違う選択肢は見つけられるだろうけど、まずは素直にそのポジションの選手から順に起用が考慮されるのは悪くない。

一方のセレッソはGKがキム・ジンヒョンに戻った。先に試合内容に少しだけ触れると、この存在は本当に大きくて浦和のプレスはかなり効果を薄くされたところがある。また、この試合のセレッソはキックオフからかなりのハイプレスを仕掛けてきた。もう少し落ち着いた入りをしてどこかでスイッチを入れてくるんじゃないかという予想をプレビューでしていたので、そこは素直に外れた。だから、リカルド・ロドリゲス監督の初手を私が批判するのはちょっとずるいかなと思っている。
盤面を解決するために、敵陣に手をつけるのが良かったのでは
この試合のスタートに関しては、セレッソボールのところを見るのが良いと思う。というのも、セレッソは鈴木をアンカーに落として、奥埜がインサイドハーフ化、上門が前線から降りてくる4-3-3変化をしていた。これは浦和が夏場以降で基本にしている形であり、浦和もスタート時点では同じやり方をしていたので、ある意味では正しく「ミラーゲーム」ということもできる。セレッソの小菊監督とリカさんは、もし2人でサッカーの話をさせたら共感する割合の多そうなタイプかなという印象もある。ただ、浦和はこの4-3-3変化に対して初戦を1-1で終えているアドバンテージの意識がリスクテイクを妨げたのかもしれない。
(残り 3443文字/全文: 4496文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


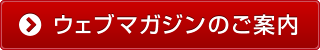
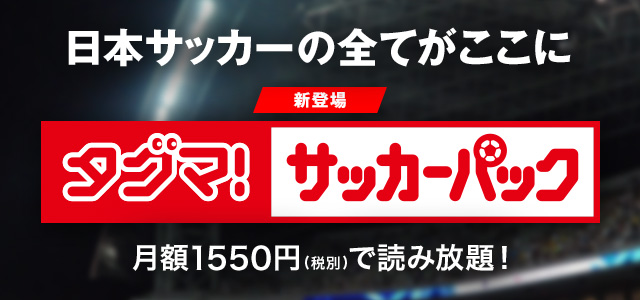





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ